運用型広告
Google・Yahoo!のリスティング広告はもちろん、Facebook・Instagram・LINE・XなどのSNS広告も運用が可能です。
セールス
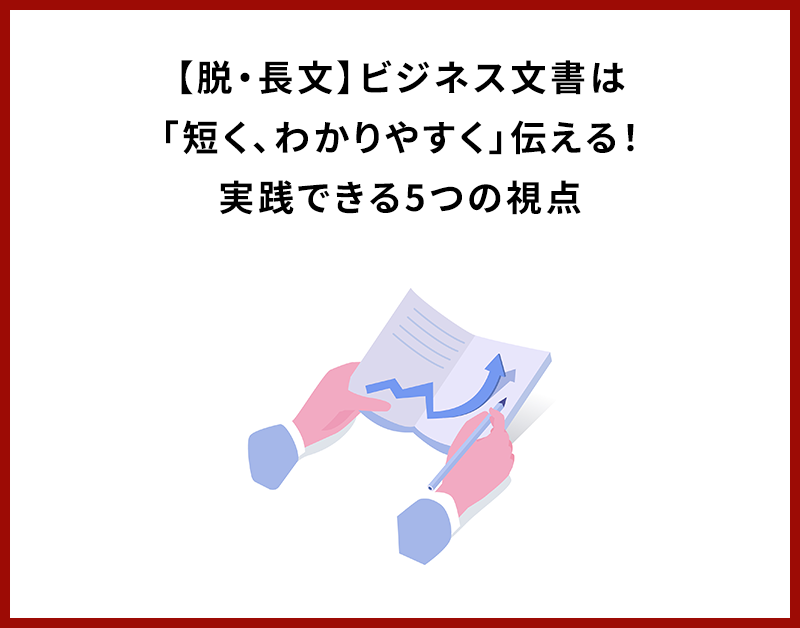
「長い方が詳しく伝わるから問題ない」。そう考えているビジネスパーソンは少なくありません。
しかし、その“丁寧な長文”が、「わかりづらさ」や「読解ストレス」を生み、結果として信頼を損なう原因になっているとしたらどうでしょうか?
特にメール、提案書、報告書など、迅速な意思決定が求められるBtoBのコミュニケーションにおいては、文章の長さは重大なボトルネックになり得ます。
今回は、日々の業務で「ついつい長文になってしまう…」とお悩みの方へ、読み手がスッと理解できる「短く伝える文章術」を、具体的な改善策とともにご紹介します。
目次
以下の2つの文章を比べてみてください。どちらがスムーズに頭に入ってくるでしょうか?
| 比較項目 | 長い文章(リライト前) | 短い文章(リライト後) |
| 例 | 社内で利用しているコミュニケーションツールにおいて、今回のプロジェクトの進捗状況をメンバーに対して、まずは手短に共有させていただきたいと思います。 | 今回のプロジェクトの進捗を、社内ツールで共有します。 |
誰が読んでも、右の方がスッと理解できるはずです。伝わっている情報量に大きな差はありませんが、読解にかかるストレスは段違いです。
この違いは、ズバリ「冗長表現」の排除にあります。
読み手のストレスを減らし、成果につながる文章を作るために実践すべき5つのポイントです。
読点で内容を繋げすぎないことが非常に大切です。
表現に深みは増しますが、簡潔さとは両立しません。伝わる文章を目指すなら、潔く削りましょう。
接続詞は文の流れを示す「ウィンカー」のような役割を果たします。上手く使えばスムーズですが、多すぎると流れを遮り、文章がゴツゴツと読みにくくなります。
「頭痛が痛い」のような極端な重複は気づきやすいですが、無意識に使ってしまう表現があります。
| 誤りやすい表現 | 改善例 |
| 各項目ごとに | 各項目で / 項目ごとに |
| まず最初に | まず / 最初に |
| すべてを網羅した | 網羅した |
一文に多くの情報が盛り込まれる場合は、無理に文章にしようとせず、箇条書きや表で整理するのがベストです。
施策Aでは、集客バナーのクリック率が前月比で1.5倍に改善し、施策Bでは、記事コンテンツ内からサイトの主要ページへの導線が明確になったため、コンバージョン率が20%向上しました。
クライアントや社内向けなど、相手によって「どこまで詳しく伝える必要があるか」は大きく変わります。
報告書や提案書でつい長文になってしまう時は、ぜひ以下のプロセスを試してみてください。
伝わる文章は、「どれだけ情報を削ぎ落とせるか」が鍵です。この視点を持ち、読み手の時間とストレスを奪わないコミュニケーションを実践しましょう。

Webマーケティングにおけるパフォーマンス改善のための資料がダウンロードできます。