運用型広告
Google・Yahoo!のリスティング広告はもちろん、Facebook・Instagram・LINE・XなどのSNS広告も運用が可能です。
Web制作
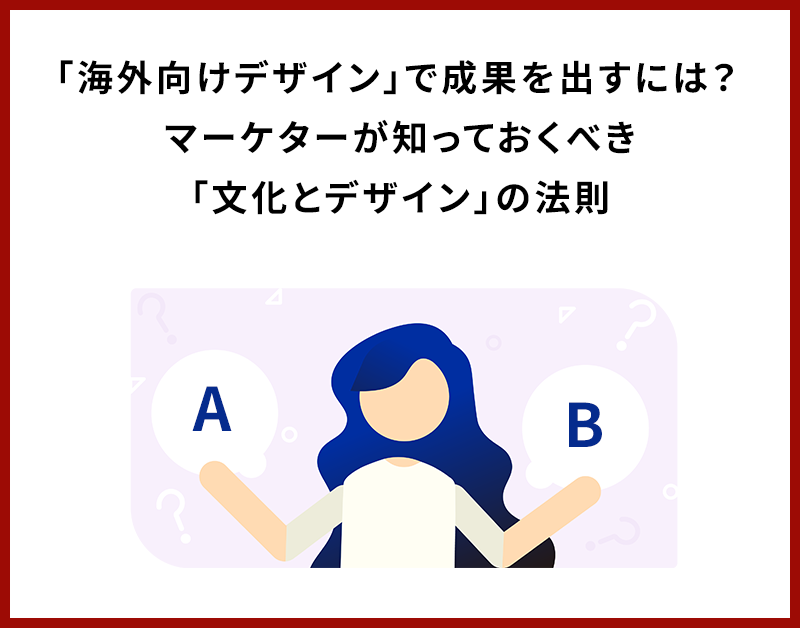
マーケティング担当者の皆様、こんにちは。
国内市場での確固たる基盤を築いた後、海外市場への展開をご検討される企業様が近年大幅に増加しています。特にデジタル領域では、以前に比べて格段に海外展開への敷居が低くなりました。
今回は、私たちが携わってきた海外デジタルマーケティング案件での知見に基づき、「日本と海外のデザイン・文化の違い」に焦点を当ててご紹介します。
国内で成功した施策をそのまま海外に適用しても、成果に結びつかないケースは少なくありません。海外展開を成功させるために、現地のユーザーの「常識」や「感性」を深く理解することが不可欠です。
目次
まず、海外市場に目を向けることの戦略的な価値を改めて整理しましょう。
初期段階で低リスクな施策を通じて、グローバル市場における自社サービスへの潜在的な需要をスピーディに検証できます。初期の感触が良ければ、本格的な海外展開へとスムーズに移行することが可能です。
現地の法規制や煩雑な契約手続きなどを気にせず、デジタル配信プラットフォームを活用することで、迅速な市場参入が実現できる時代です。
しかし、この「手軽さ」ゆえに、文化の違いを見落としてしまうリスクも伴います。
日本の常識が、世界の常識とは限りません。最も分かりやすい例が「正解・不正解」を示す記号や色の認識です。
| 項目 | 日本での一般的な認識 | 海外(特に欧米)での一般的な認識の例 | 違いがもたらすリスク |
| 「正解」の記号 | 〇 | ✓(チェックマーク) | 「〇」は海外では「数字のゼロ」や「問題なし(OK)」を意味し、正解とは限らない |
| 「不正解」の記号 | × | ×(バツマーク) | 日本と同じ場合もあるが、「✗」は単純な間違いを意味せず、使用を避ける文化圏もある |
| 「正解」の色 | 赤(〇とセットで) | 緑 | 赤は多くの国で「危険」「停止」「エラー」を意味する |
| 「不正解」の色 | 青(×とセットで) | 赤 |
このように、ウェブサイトやデジタルプロダクトのデザインにおいて、この小さな「色彩の文化差」や「記号のローカライズ」を誤ると、ユーザーに誤解や混乱を招き、離脱率の増加に直結します。
国によって色の印象が変わるように、ユーザーが効果的だと感じるWebサイトデザインも大きく異なります。
世界的な大手飲食チェーンの各国サイトを比較してみると、その違いが明確です。(ここでは、その企業Aのサイト構造を参考に、一般的な各国ユーザーの傾向を分析します)
| 国名 | Webサイトデザインの主な傾向 | ユーザーの行動・価値観の背景 |
| 日本 | 利便性重視、情報量重視。1ページに情報を詰め込み、豊富なメニューやバナーで構成。詳細な説明を好む。 | スクロール量を減らして「すぐに情報を知りたい」という利便性を重視する傾向。 |
| 米国 | シンプルイズベスト、イメージ重視。大きな画像1枚でブランドイメージを伝え、機能は最小限。まず興味を引くことを優先。 | 直感的な印象や世界観を重視する傾向が強い。 |
| 中国 | デザイン性重視、簡潔な構成。2カラム構成でコンテンツを充実させつつも、フォントやバナーの装飾にこだわる。 | 派手なものや装飾性の高いものを好む生活文化が反映されている。 |
| インド | 説明重視、情報密度が高い。画像よりも文字情報が目立ち、商品の価格や詳細情報をトップページに集約。 | 書籍を読む文化が強く、詳細な説明や網羅性を求める傾向。 |
これらの傾向は、バナーデザインにも現れます。日本は商品イメージに合わせた様々な装飾が多いのに対し、欧米では商品をシンプルかつ正面から捉えた、「メッセージを明確に伝える」デザインが主流です。
海外配信では、デザインだけでなく、実際に使用する「言葉」のローカライズも成果を大きく左右します。弊社の検証で得られた知見を共有します。
| 要素 | 日本語での検索傾向 | 英語での検索傾向 | マーケティングへの示唆 |
| キーワード | 「単語の羅列」で検索する傾向が強い。(例:「安価 スキー 日本」) | 「文章・質問形式」での検索が多い。(例:「cheapest ski resort in japan」) | 現地の人が「日常会話でどのように質問するか」を想定したキーワード設定が不可欠。 |
| 広告文 | 比較的、平易な説明文が好まれる。 | 呼びかけ風や「!」「?」などの記号を活用した表現の方が、クリック率とコンバージョン率が高い傾向にありました。 | 日本よりもストレートで情熱的な訴求が効果的である可能性が高い。 |
いかがでしたでしょうか。
海外のサイトを観察すると、その国の文化や人々の普段の生活面がデザインや情報構成に色濃く反映されていることが分かります。
異なる文化への視点を持つことは、国内マーケティングにおけるペルソナ理解を深めるヒントにもなります。例えば、「新聞を読む世代には文字を多めに」「若年層には視覚的な訴求を」というように、ターゲットが「何を重視し、どう行動するか」をデザインやコピーから逆算する習慣が身につくはずです。
国内に閉じることなく、たまにはグローバルな視点で情報やデザインをインプットし、皆様のB2Bマーケティング戦略をさらに洗練させるヒントとしてご活用ください。

Webマーケティングにおけるパフォーマンス改善のための資料がダウンロードできます。