運用型広告
Google・Yahoo!のリスティング広告はもちろん、Facebook・Instagram・LINE・XなどのSNS広告も運用が可能です。
広告運用
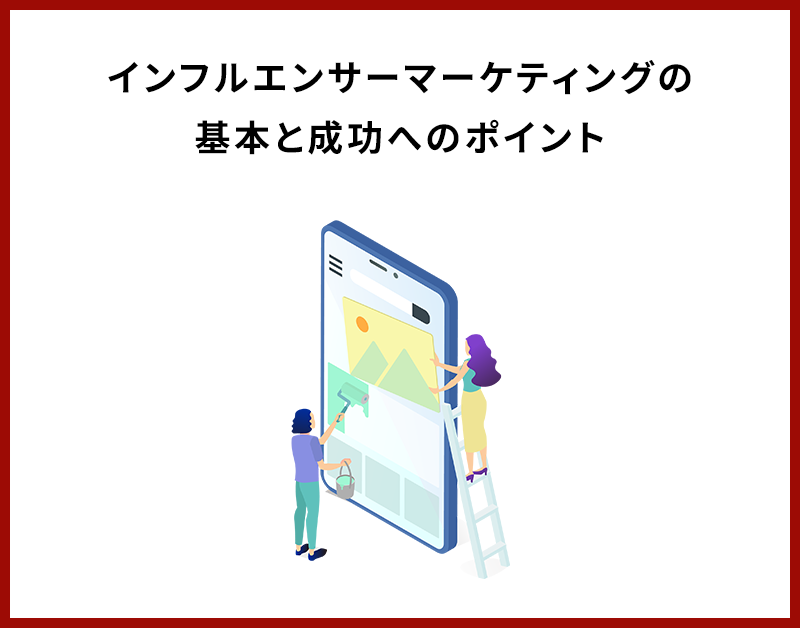
最近、クライアント様との商談や、業界の動向を見ていると、「インフルエンサーマーケティング」の話題に触れる機会が増えています。特に、CPA(顧客獲得単価)を効果的に抑えながら成果を上げている事例も増えており、そのポテンシャルに注目が集まっていますね。
そこで今回は、「そもそもインフルエンサーマーケティングとは?」という基本から、BtoB事業者が知っておくべき施策内容や成功のための注意点まで、フランクにご紹介していきます!
目次
主にInstagram、YouTube、X(旧Twitter)、TikTokなどのSNSで多くのフォロワーやファンを抱える「インフルエンサー」に、自社の商品やサービスを宣伝してもらい、その影響力と「口コミ効果」で集客や購買を促すマーケティング手法です。
情報過多の現代において、企業からの直接的な広告よりも、「信頼できる人が勧めている」という親近感と信頼性が重視されるようになっています。
インフルエンサーマーケティングは、単に商品をプレゼントするだけではありません。目的や商材に応じて多様な施策が可能です。
インフルエンサーが紹介した商品を購入したり、サービスを利用したりする消費者は非常に高い割合を占めているという調査結果があります。これは、彼らの発信が「広告」ではなく「信頼できる情報」として受け止められている証拠です。
インフルエンサーの費用感は、その拡散力(リーチ力)に比例して変動しますが、一般的にはフォロワー数に応じた目安が存在します。編集コストの高い動画コンテンツなどを依頼する場合は、さらに費用が大きくなる傾向にあります。
効果を最大化するためには、ただフォロワーが多い人を選ぶのではなく、下記のような「質」を見極めることが重要です。
インフルエンサーマーケティングは強力ですが、リスクも伴います。メリットとデメリットを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
| メリット | デメリット |
| 柔軟かつ多様な施策 | ステマ(ステルスマーケティング)のリスク |
| 口コミによる集客効果 | SNS炎上のリスク |
| 広告っぽくないため信頼性アップ | 景表法・薬事法違反のリスク |
特に、2023年10月以降はステマ規制が強化されています。インフルエンサーには、投稿内に「PR」や「広告」といった明記を徹底してもらい、法的なリスク管理を徹底しましょう。
今回はインフルエンサーマーケティングの基本と、実施する上での注意点をご紹介しました。
「私たちの事業には関係ないかも?」と思われがちですが、例えば展示会への集客や、専門性の高いサービスの認知拡大など、BtoB領域でも活用できる可能性は十分にあります。
もし、貴社のプロモーション戦略でインフルエンサー活用にご興味があれば、ぜひ一度、通常のマーケティング手法と比較検討しながら、お気軽にご相談ください。私たちも、お客様の事業に役立つよう、常に最新の知見とアイデアを提供し続けてまいります!

Webマーケティングにおけるパフォーマンス改善のための資料がダウンロードできます。